お笑い第7世代とは?意味と定義をわかりやすく解説
「お笑い第7世代」とは、2010年代後半から台頭してきた若手芸人たちを指す言葉です。霜降り明星・ハナコ・EXIT・かが屋など、テレビやYouTubeなど多方面で活躍する芸人が多く含まれています。
この言葉は、芸人たち自身が名乗り始めたわけではなく、テレビ業界やメディアが若手芸人をカテゴライズする中で自然と浸透していきました。特に「霜降り明星のせいや」がバラエティ番組内で発言したことをきっかけに話題となり、一気に広まりました。
「第7世代」という言葉が生まれた背景
1. 若手芸人ブームの再燃
2000年代後半〜2010年代にかけて、お笑い界はベテラン勢の活躍が目立つ時期でした。ダウンタウンやナインティナイン、くりぃむしちゅー、バナナマンといった中堅・大御所がテレビを席巻し、若手芸人が台頭しづらい環境が続いていました。
しかし、2018年の『M-1グランプリ』で霜降り明星が最年少優勝を果たしたことが転機となり、「若手芸人でも頂点を取れる」という風潮が広まります。これをきっかけに、新しい世代の芸人たちが次々と注目され始めたのです。
2. テレビ業界の世代交代意識
同時期、テレビ番組側も新しいスターを求めていました。SNSやYouTubeなど新しいメディアが浸透し、若年層の視聴者がテレビから離れつつある中で、フレッシュな芸人の存在が必要とされていたのです。
この流れを受けて、霜降り明星やEXITなどを中心とした若手芸人を「第7世代」として括り、メディア全体でのムーブメントが形成されていきました。
第7世代の代表的な芸人一覧
お笑い第7世代を代表する芸人たちは、個性もジャンルも多彩です。ここでは主な人気芸人を紹介します。
霜降り明星(せいや・粗品)
お笑い第7世代の象徴的存在。2018年『M-1グランプリ』で最年少優勝を果たし、一気にブレイク。せいやのテンポの良いツッコミと粗品の独特なワードセンスが特徴です。テレビ・ラジオ・YouTubeなどあらゆるメディアで活躍中。
EXIT(りんたろー。・兼近大樹)
チャラ男キャラで登場しつつも、実は社会問題にも意欲的に取り組むなど、新時代を象徴する芸人コンビ。YouTube活動やファッション分野でも人気を集め、Z世代からの支持が厚い。
ハナコ(菊田竜大・秋山寛貴・岡部大)
『キングオブコント2018』優勝。演技力の高さと構成力が光るコント師として高く評価されています。岡部大は俳優としても多数のドラマに出演。
かが屋(加賀翔・賀屋壮也)
リアリティと細やかな描写を得意とするコントコンビ。若手コント職人として業界内での評価が非常に高く、「演技派コント師」として多くのファンに支持されています。
四千頭身
トリオならではの独特な間とゆるい会話で人気を博した若手トリオ。SNS時代にマッチしたライトな笑いを提供し、「脱力系漫才」の先駆者として注目されています。
他のお笑い世代との違い
お笑い界では、世代ごとに特徴があります。ここでは、「第3世代」「第4世代」「第5世代」「第6世代」と比較して、第7世代の特徴を整理します。
| 世代 | 主な芸人 | 特徴 |
|---|---|---|
| 第3世代 | ダウンタウン、とんねるず、ウッチャンナンチャン | テレビバラエティの黄金期を作り上げた革新世代 |
| 第4世代 | ナインティナイン、ロンドンブーツ1号2号、雨上がり決死隊 | バラエティとトーク力で全盛期を築いたスター世代 |
| 第5世代 | アンタッチャブル、サンドウィッチマン、タカアンドトシ | 実力派漫才・コント師として高評価。安定感のある芸風 |
| 第6世代 | オードリー、千鳥、かまいたち | トーク・バラエティ・ロケで万能型。今のテレビを支える中核 |
| 第7世代 | 霜降り明星、EXIT、ハナコ、かが屋、四千頭身 | SNS・YouTube時代に適応。多様性と個性重視の新世代 |
第7世代の最大の特徴
- SNS・YouTubeを活用したセルフプロデュース
→ テレビだけでなく、ネット発信によって人気を拡大。 - ファッション性・カルチャー性の高さ
→ 若者文化と親和性が高く、芸人=ダサいというイメージを覆した。 - ネガティブよりポジティブな笑い
→ ツッコミも攻撃的でなく、誰も傷つけない笑いを重視。
なぜ「第7世代」は支持されたのか?
1. 多様性を尊重する時代背景
ジェンダーや価値観の多様性が求められる現代において、第7世代の芸人たちは「優しさ」や「共感」を武器にしています。彼らの笑いは、かつてのような上下関係やいじりの強い構造ではなく、フラットで温かい雰囲気を生み出しています。
2. SNSでの発信力
YouTubeやTikTokでの発信を通じて、テレビを見ない層にもリーチできるのが第7世代の強み。霜降り明星の「しもふりチューブ」やEXITの「EXIT Charannel」など、登録者数100万人を超えるチャンネルも複数存在します。
3. テレビ以外の活躍の場
NetflixやABEMA、YouTubeなど、プラットフォームが多様化した今、第7世代はメディアを横断して活動。自分たちのペースで笑いを届けられる新時代の芸人像を体現しています。
第7世代の今とこれから
「第7世代」という言葉が誕生してから数年が経ち、彼らはもはや“若手”ではなく、“中堅”へと成長しつつあります。霜降り明星の粗品はMCや音楽活動、EXITの兼近は社会的活動、かが屋はドラマ出演など、それぞれが独自の道を歩み始めています。
お笑い界全体が多様化する中で、第7世代は「個の時代」を象徴する存在として、今後も新たなスタイルを発信し続けるでしょう。
まとめ:第7世代が変えた“笑い”のスタンダード
- 第7世代とは? → 2010年代後半に登場した新世代の若手芸人。
- 誕生の背景 → 霜降り明星のM-1優勝をきっかけにムーブメント化。
- 代表芸人 → 霜降り明星、EXIT、ハナコ、かが屋、四千頭身など。
- 特徴 → 優しさ・多様性・SNS発信力。
- 今後の展望 → 個性と発信力で、テレビ以外の笑い文化をリード。
以上が「お笑い第7世代」についての完全解説です。彼らが生み出す“新しい笑い”は、これからのお笑い史を間違いなく塗り替えていくことでしょう。
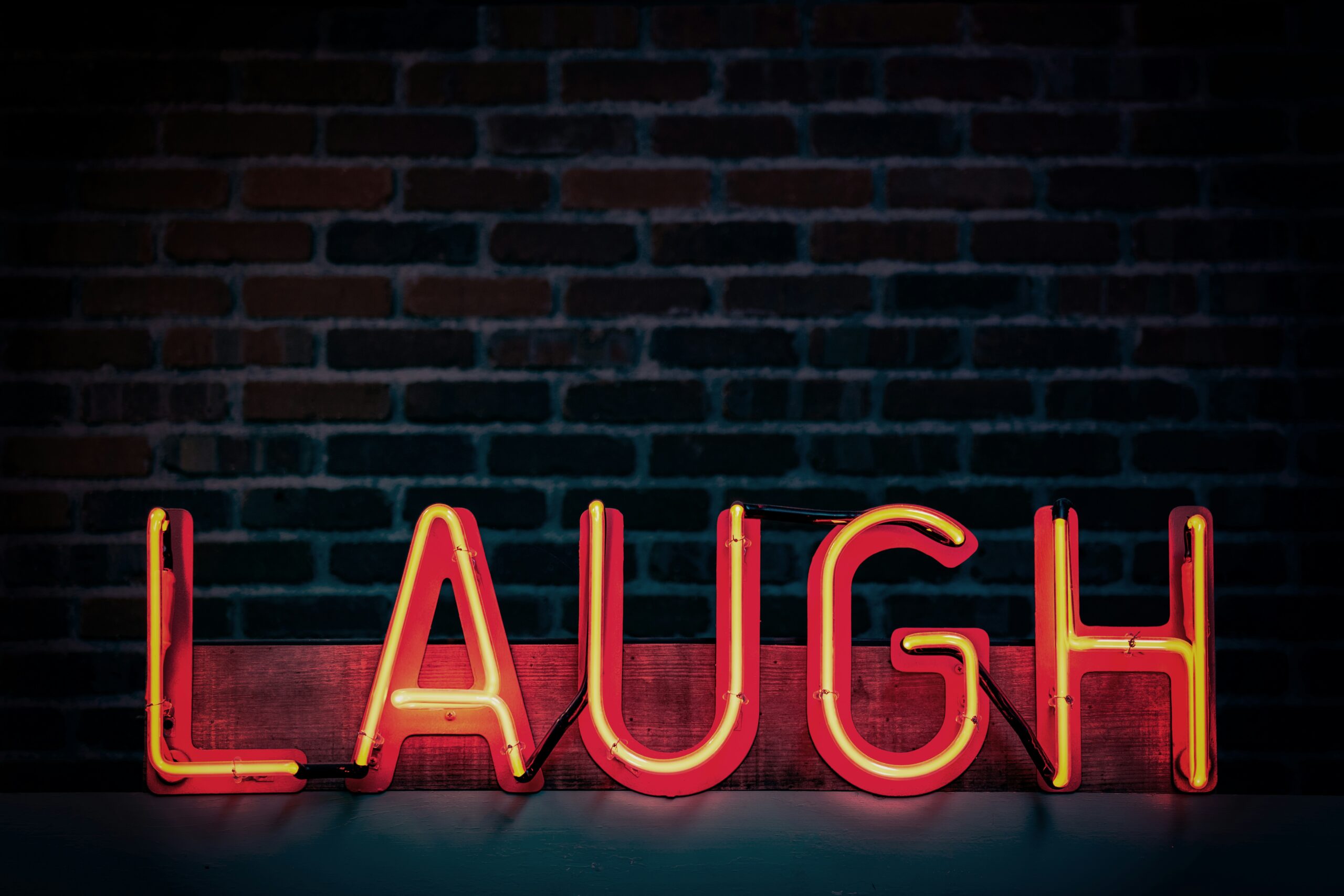


コメント